就職や転職の際に必ず作成する履歴書。一見シンプルに見えるこの書類ですが、学歴や職歴の記載方法一つで採用担当者に与える印象が大きく変わります。特に履歴書における学歴と職歴の書き方や順番は、応募者の経歴を端的に伝える重要な要素です。この記事では、履歴書における学歴と職歴の正しい順番や効果的な書き方について詳しく解説していきます。採用を勝ち取るための履歴書作成のコツをマスターしましょう。
履歴書に必要な学歴と職歴の順番
学歴の重要性と基本構成
履歴書における学歴は、応募者の基礎的な教育背景を示す重要な情報です。多くの採用担当者は、応募者の学習能力や専門知識の基盤を理解するために学歴欄に目を通します。基本的に学歴は「新しいもの順」ではなく「古いもの順」に記載するのが一般的です。つまり、最初に中学校または高校から始めて最終学歴に向かって時系列に沿って記載していくのです。
この時系列に沿った記載方法は、採用担当者が応募者の教育履歴をスムーズに追えるようにするためです。特に日本の採用システムでは、一貫した経歴の流れを重視する傾向があります。学歴欄では中学校(または高校)からスタートし、大学や大学院、専門学校などの最終学歴まで順を追って記載することで、応募者の成長過程や学びの道筋を明確に示すことができます。
また、学歴の書き方には「学校名」「入学年月」「卒業年月」「学部・学科名」などの基本情報を漏れなく記載することが求められます。これらの情報が整理されて記載されていることで、応募者の基礎的な情報管理能力も同時にアピールすることができるのです。
職歴を効果的に記載するポイント
職歴は応募者の実務経験や仕事に対する姿勢を示す重要な項目です。職歴の記載も学歴と同様に「古いものから新しいものへ」と時系列順に記入するのが基本です。職歴欄では「会社名」「入社年月」「退職年月」「職務内容」などを明確に記載することが重要です。
効果的な職歴の記載には、単に会社名や在籍期間を書くだけでなく、その会社でどのような役割を担い、どのような成果を上げたのかを簡潔に伝えることがポイントです。特に応募先の企業が求める能力や経験と関連する職務経験は、少し詳しく記載することで自身の強みをアピールすることができます。
また、職歴の空白期間がある場合も正直に記載することが大切です。無理に隠そうとすると、面接時に矛盾が生じる可能性があります。空白期間があった場合でも、その期間に自己啓発や資格取得のための勉強をしていたなどの前向きな活動をしていたのであれば、それを簡潔に説明することでむしろ積極性をアピールすることができるでしょう。
履歴書の記入順序はどこから始めるべきか
履歴書全体の記入順序としては、まず個人情報(氏名、住所、連絡先など)から始め、次に学歴、職歴という順番で記載するのが一般的です。しかし実際に記入を始める際には、書き間違いを防ぐために下書きを先に行い確認してから清書するのがおすすめです。
特に日付や会社名、学校名などの固有名詞は正確に記載する必要があるため、事前に確認しておくことが重要です。また履歴書の種類によって記入欄の配置が異なる場合がありますので、使用する履歴書のフォーマットをよく確認してから記入を始めるようにしましょう。
多くの場合、履歴書の右上に写真を貼り、その下に署名・捺印をするスペースがあります。写真は応募先企業の採用担当者に第一印象を与える重要な要素ですので、適切な服装で撮影した鮮明なものを用意することが大切です。写真の裏面には念のため氏名を記入しておくとよいでしょう。
履歴書に記載する学歴の書き方
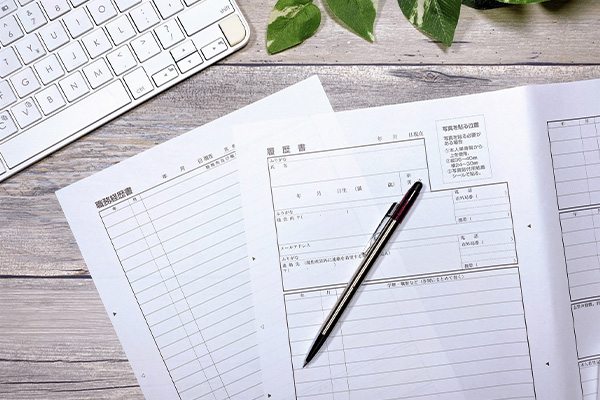
最終学歴の記入方法
最終学歴とは、応募者が最後に卒業した学校のことを指します。履歴書における最終学歴の記入は特に重要視されます。なぜなら、それが応募者の基本的な教育レベルや専門知識の深さを示す指標となるからです。
最終学歴の記入方法としては、「〇〇大学〇〇学部〇〇学科 卒業」というように学校名、学部名、学科名を明記し、最後に「卒業」と記載します。大学院を修了している場合は、「〇〇大学大学院〇〇研究科〇〇専攻 修了」と記入します。
中途退学の場合は「中退」と正直に記載することが基本です。中退していても、その後に専門的なスキルを身につけたり実務経験を積んだりしていれば、それを職歴や資格欄でアピールすることができます。また留学経験がある場合は、その経験も学歴に含めて記載することで語学力や国際感覚をアピールすることができるでしょう。
学校名と入学・卒業年度の記載
学歴欄における学校名と入学・卒業年度の記載は、履歴書の基本中の基本です。学校名は正式名称を使用し、略称は避けるのが原則です。例えば「〇〇大学」ではなく「学校法人〇〇大学」というように正式名称で記載します。
入学年月と卒業年月は、「令和2年4月入学」「令和6年3月卒業」というように、年号(和暦または西暦)と月を明記します。西暦と和暦のどちらを使用するかは統一することが大切です。また、現在も在学中の場合は「令和6年4月入学」「令和10年3月卒業見込み」というように「卒業見込み」と記載します。
学校の統廃合により校名が変更されている場合は、入学時の校名ではなく卒業時の校名を記載するのが一般的です。また編入学した場合は、前の学校の情報も含めて時系列順に記載することが望ましいでしょう。
私立・公立の学校の扱いについて
学校名を記載する際に、私立・公立の区別を明記するかどうかについては、特に決まりはありません。しかし、一般的には私立の場合は「私立〇〇高等学校」、公立の場合は「〇〇県立〇〇高等学校」「〇〇市立〇〇中学校」というように記載することが多いです。
ただし私立大学の場合は単に「〇〇大学」と記載しても問題ありません。公立大学の場合は「〇〇県立大学」「〇〇市立大学」というように設置者を明記することが一般的です。国立大学の場合は「〇〇大学」と記載します。
学校名の記載において重要なのは、正確さと一貫性です。特に採用担当者が確認のために問い合わせをする可能性がある情報ですので、正確に記載することを心がけましょう。また海外の学校を卒業している場合は、日本語訳と併せて原語の学校名も記載するとよいでしょう。
職歴の書き方と記載例
職務経歴書との違いと役割
履歴書の職歴欄と職務経歴書は、どちらも応募者の職業経験を示すものですがその役割と詳細さには違いがあります。履歴書の職歴欄は、勤務先の会社名、在籍期間、役職名などの基本情報を簡潔に記載するものです。一方、職務経歴書は職歴の詳細な内容、担当業務、実績、スキルなどを具体的に記載するものです。
履歴書の職歴欄は限られたスペースの中で、応募者の職業経験の概要を時系列に沿って示すことが目的です。そのため、会社名、入社・退社年月、役職名、簡単な業務内容を簡潔に記載します。これに対して職務経歴書では、各職場での具体的な業務内容や成果、習得したスキル、担当したプロジェクトなどを詳細に記載します。
応募先企業の採用担当者は、履歴書の職歴欄で応募者の経歴の概要を把握し職務経歴書でその詳細を確認します。そのため履歴書の職歴欄は全体の流れが分かりやすいように簡潔に記載し、詳細は職務経歴書に委ねるという役割分担を意識することが大切です。
アルバイトや派遣社員の経験をどう書くか
正社員としての職歴だけでなく、アルバイトや派遣社員としての経験も応募先の職種に関連する内容であれば積極的に記載するとよいでしょう。特に新卒者や職歴の少ない応募者にとって、アルバイト経験は貴重なアピールポイントになります。
アルバイトや派遣社員の経験を記載する際は、「〇〇株式会社(アルバイト)」「〇〇株式会社(派遣社員)」というように雇用形態を明記します。在籍期間も正確に記載し、どのような業務に携わったのかを簡潔に記載するとよいでしょう。
また長期間継続して同じ職場でアルバイトをしていた場合は、その継続性自体が応募者の真面目さや責任感をアピールすることになります。逆に短期間で複数のアルバイトを転々としている場合は、関連性のある重要なもののみを選んで記載することも検討するとよいでしょう。
具体的な業務内容をアピールする方法
履歴書の職歴欄では、単に在籍していた期間や会社名を記載するだけでなく、具体的にどのような業務に携わり、どのような成果を上げたのかを簡潔にアピールすることが重要です。ただし、詳細な業務内容は職務経歴書に記載するものなので、履歴書では要点のみを記載するようにしましょう。
具体的な業務内容をアピールする際は、応募先企業が求めている能力や経験と関連付けて記載することがポイントです。例えば営業職に応募する場合は過去の営業成績や顧客対応の経験を、事務職に応募する場合は事務処理能力や正確性を求められる業務経験をアピールするとよいでしょう。
また数字で表せる実績があれば、それを具体的に記載することも効果的です。例えば「売上20%増加に貢献」「月間処理件数300件を担当」など、具体的な数字で実績を示すことで応募者の能力や成果がより明確に伝わります。
履歴書作成時の注意点とポイント
記載の順番における注意事項
履歴書における記載順序は、基本的に時系列順に従って古いものから新しいものへと記載していきます。しかし学歴と職歴の始まりをどこからにするかについては、いくつかの考え方があります。
一般的には、学歴は義務教育終了後の高校から記載することが多いですが中学校から記載するケースもあります。特に指定がない場合は、高校からの記載で問題ありません。ただし応募先企業から特別な指示がある場合は、その指示に従って記載することが大切です。
職歴については、現在の仕事に関連する経験からスタートしたいと考える方もいますが、基本的には最初の就職先から時系列順に記載するのが原則です。ただしアルバイトや派遣など多数の職歴がある場合は、応募先に関連する重要なものを選んで記載することも一つの方法です。
また学歴と職歴の空白期間については、その理由を簡潔に記載することが望ましいです。例えば、「〇〇年〇月~〇〇年〇月 資格取得のため勉強」「〇〇年〇月~〇〇年〇月 海外留学」などと記載することで、空白期間の説明ができます。
西暦と和暦の統一について
履歴書における日付の記載方法として、西暦と和暦のどちらを使用するかは応募者の自由です。ただし、一度選んだら全体を通して統一することが大切です。つまり学歴に西暦を使用したなら職歴も西暦で、和暦を使用したなら全体を和暦で統一するということです。
和暦を使用する場合は、「平成」「令和」などの元号を正確に使い分ける必要があります。例えば、平成から令和に変わった2019年5月1日以降は「令和元年」と記載します。西暦を使用する場合は「2019年」というように記載します。
どちらを選ぶかについては、応募先企業の雰囲気や業界の慣習を考慮するとよいでしょう。伝統的な日本企業では和暦が好まれる傾向がありますが、外資系企業や国際的な企業では西暦が一般的です。迷った場合は、応募先企業の求人票や公式サイトの日付表記を参考にするとよいでしょう。
学校名や職種の正式名称を使用する重要性
履歴書に記載する学校名や会社名、役職名などは、必ず正式名称を使用することが重要です。略称や通称ではなく、正式名称を記載することで応募者の正確さと丁寧さをアピールすることができます。
例えば、「〇〇大」ではなく「〇〇大学」、「〇〇株」ではなく「〇〇株式会社」というように正式名称を使用します。また役職名も「リーダー」ではなく「チームリーダー」、「課長」ではなく「営業課長」というように具体的な役職名を記載するとよいでしょう。
正式名称が分からない場合は、インターネットで調べるか直接学校や会社に問い合わせて確認することをおすすめします。特に会社名は合併や社名変更などにより変わっている可能性もありますので、在籍当時の正式名称を使用することが大切です。
学歴と職歴の記入が採用に与える影響

学歴が持つ意味と職種の関連性
履歴書における学歴の重要性は、応募する職種や企業によって異なります。例えば研究職や専門職では、関連する学部や学科での専門教育が重視されます。一方、営業職や事務職などでは学歴よりも職歴や人柄、コミュニケーション能力などが重視される傾向があります。
特に新卒採用の場合は、職歴がないため学歴が重要な判断材料となります。大学での専攻や研究テーマ、取得した資格などが応募者の知識や能力を示す指標となるのです。一方、中途採用の場合は学歴よりも直近の職歴や実績が重視される傾向があります。
ただし、いかなる場合でも学歴を偽ったり誇張したりすることは避けるべきです。採用プロセスの中で虚偽が発覚した場合、それだけで不採用になる可能性が高いですし採用後に発覚した場合でも信頼を失うことになります。正直に記載し、自分の強みを別の形でアピールする方が賢明です。
職歴の強みが採用にどう働きかけるか
職歴は応募者の実務経験や能力を直接的に示す重要な情報です。特に中途採用の場合、職歴は採用の可否を大きく左右します。職歴を通じて、応募者がどのような業界や職種で経験を積み、どのようなスキルや知識を身につけてきたのかを採用担当者は判断します。
職歴の強みを採用に活かすためには、応募先企業が求めている能力や経験と自分の職歴をうまく関連付けることが重要です。例えば異なる業界からの転職の場合でも、共通するスキルや経験を強調することで自分の適性をアピールすることができます。
また、職歴における実績や成果を具体的に示すことも効果的です。単に「営業を担当」と記載するよりも、「新規顧客開拓で月間目標の120%を達成」というように具体的な成果を記載することで、応募者の能力や貢献度がより明確に伝わります。
志望動機との関連性を考える
履歴書における学歴と職歴の記載は、志望動機と整合性を持たせることが重要です。応募者の学歴や職歴と志望動機がつながっていることで、キャリアプランの一貫性や応募先企業への熱意が伝わります。
例えば、大学で経営学を専攻し営業職の経験を積んできた応募者が、マーケティング部門への転職を希望する場合、「大学で学んだ経営学の知識と営業職で培った顧客理解力を活かしてマーケティング戦略に貢献したい」というように、学歴と職歴を志望動機に関連付けることができます。
逆に、学歴や職歴と志望動機に大きなギャップがある場合は、なぜその職種や企業を志望するのかを明確に説明する必要があります。例えば全く異なる業界からの転職の場合、なぜその業界に興味を持ったのか、どのようなスキルや経験が活かせると考えているのかを説明することで志望の真剣さをアピールすることができます。
履歴書の具体的な記入例
成功する履歴書の見本
成功する履歴書の特徴は、情報が整理されており読み手にとって分かりやすいことです。以下に、学歴と職歴の記入例を示します。
学歴の記入例: 「平成22年4月 〇〇県立〇〇高等学校 入学 平成25年3月 同校 卒業 平成25年4月 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 入学 平成29年3月 同大学同学部同学科 卒業」
職歴の記入例: 「平成29年4月 株式会社〇〇 入社 営業部配属 令和2年7月 同社 営業部主任に昇進 令和4年9月 同社 退職 令和4年10月 株式会社△△ 入社 マーケティング部配属 現在に至る」
このように時系列順に整理し、入学・卒業、入社・退職の年月を明確に記載します。また昇進や部署移動などの情報も記載することで、キャリアの成長過程が分かりやすく伝わります。
不備を避けるためのチェックリスト
履歴書を完成させた後は、以下のチェックリストを使って不備がないか確認しましょう。
- 学歴と職歴の期間に空白がないか
- 学校名や会社名は正式名称で記載されているか
- 西暦と和暦は統一されているか
- 記載順序は時系列順になっているか
- 入学・卒業、入社・退職の年月は正確か
- 学部・学科名、役職名は具体的に記載されているか
- 誤字脱字はないか
- 現在の状況(「現在に至る」など)は明記されているか
特に日付の記載ミスは多いので、卒業証書や在職証明書などと照らし合わせて確認することをおすすめします。また、履歴書の記載内容と職務経歴書の内容に矛盾がないかも確認しましょう。
分かりやすいテンプレートの活用法
近年は市販の履歴書だけでなく、インターネット上で無料のテンプレートも多数公開されています。これらのテンプレートを活用することで、見やすく整理された履歴書を作成することができます。
テンプレートを選ぶ際のポイントは、応募先企業の業界や企業文化に合ったデザインを選ぶことです。伝統的な日本企業であれば標準的な白黒の履歴書が、クリエイティブな業界であればデザイン性のあるテンプレートが適しているかもしれません。
またテンプレートを使用する場合でも、自分の経歴や強みが効果的に伝わるようにカスタマイズすることが大切です。例えば学歴や職歴のスペースを調整したり、アピールポイントを強調したりするなど自分に合わせた修正を加えるとよいでしょう。
転職活動における履歴書の重要性
転職市場での学歴と職歴の評価
転職市場では、学歴よりも職歴や実績が重視される傾向があります。特に実務経験が豊富になるほど、出身校よりも直近の職場でどのような成果を上げてきたかが評価の対象となります。
ただし、業界や職種によっては学歴も重要な判断材料となる場合があります。例えば法律や会計、医療などの専門職では、関連する学部や学科での教育背景が重視されます。また研究開発職では、大学院での研究テーマや実績が評価されることもあります。
転職市場での評価を高めるためには、自分の強みとなる経験や実績を明確にし、それを履歴書や職務経歴書で効果的にアピールすることが大切です。例えば前職での具体的な成果や習得したスキル、担当したプロジェクトなどを具体的に記載することで、応募者の能力や貢献度をアピールすることができます。
応募先企業に応じた内容の調整方法
履歴書は応募先企業ごとにカスタマイズすることが効果的です。特に職歴の記載内容は、応募先企業が求めている能力や経験に合わせて強調するポイントを変えることをおすすめします。
例えば営業職に応募する場合は営業成績や顧客対応の経験を、管理職に応募する場合はチームマネジメントやプロジェクト管理の経験を強調するというように、応募先のニーズに合わせて自分の経験をアピールします。
また応募先企業の業界や企業文化に合わせて、履歴書のトーンや表現方法を調整することも大切です。伝統的な日本企業であれば丁寧で謙虚な表現を、グローバル企業であれば自己アピールを積極的に行うなど企業文化に合わせた表現を心がけるとよいでしょう。
実際の面接での活用法
履歴書は面接の際の重要な資料となります。面接官は履歴書を見ながら質問を準備することが多いため、履歴書に記載した内容については詳しく説明できるように準備しておくことが大切です。
特に職歴に関しては、具体的な業務内容や成果、苦労した点や学んだことなどを説明できるようにしておきましょう。また職歴に空白期間がある場合は、その理由を正直に説明する準備をしておくことも重要です。
面接では履歴書の内容に基づいて質問されることが多いため、履歴書と面接での説明に矛盾がないようにすることが大切です。また履歴書に記載しきれなかった強みや経験を面接で補足説明することで、より深く自分をアピールすることができます。
留学や転校の経験を履歴書にどう記載するか
留学経験はアピールポイントになるか
留学経験は、語学力や異文化理解力、適応力などを示す貴重なアピールポイントになります。特にグローバル展開をしている企業や外資系企業では、留学経験が高く評価されることがあります。
留学経験を履歴書に記載する際は、留学先の学校名、留学期間、取得した学位や資格などを明記します。例えば、「令和元年9月~令和2年8月 〇〇大学(アメリカ)交換留学」というように記載します。
また留学中に特別なプロジェクトに参加した経験や現地での活動などがあれば、それも簡潔に記載するとよいでしょう。ただし詳細な内容は面接で説明するか、別途留学レポートなどを用意しておくことをおすすめします。
転校した場合の記入方法と影響
転校経験がある場合は、それぞれの学校の在籍期間を時系列順に記載することが基本です。例えば、高校で転校した場合は以下のように記載します。
「平成25年4月 〇〇県立〇〇高等学校 入学 平成26年9月 同校 転出 平成26年10月 △△県立△△高等学校 転入 平成28年3月 同校 卒業」
このように転出した学校と転入した学校の両方を明記することで、教育歴の連続性が明確になります。転校の理由については履歴書に記載する必要はありませんが、面接で質問される可能性があるため簡潔に説明できるように準備しておくとよいでしょう。
転校経験自体は、一般的に採用に大きな影響を与えることはありません。ただ、頻繁に転校している場合は、その理由を聞かれる可能性が高くなります。その場合は親の転勤や引っ越しなど、やむを得ない事情であったことを説明するとよいでしょう。また転校を経験したことで得られた適応力や新しい環境での人間関係構築能力などを、ポジティブな側面としてアピールすることもできます。
経歴に記載する際の注意事項
留学や転校の経験を履歴書に記載する際の注意点は以下の通りです。
まず、日付や学校名は正確に記載することが重要です。特に海外の学校名は、原語表記と日本語訳を併記するとよいでしょう。例えば、「University of California, Los Angeles(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)」というように記載します。
次に、留学や転校が正規の教育課程の一部である場合と、個人的な選択による場合で記載方法が異なる点に注意が必要です。大学の交換留学プログラムなどの場合は、「〇〇大学在学中」という形で記載し、その下に「令和元年9月~令和2年8月 △△大学(アメリカ)交換留学」と記載するとよいでしょう。
また海外の教育制度と日本の教育制度の違いにより、卒業年度や学年の対応が難しい場合もあります。その場合は、日本の教育制度に換算して記載するか、備考欄などで補足説明を加えるとよいでしょう。
留学や転校の経験は、適切に記載することで応募者の多様な経験や柔軟性をアピールする良い機会となります。しかし事実と異なる内容を記載することは避け、正確な情報を提供することを心がけましょう。
履歴書の送付方法とマナー

郵送時の封筒の選び方
履歴書を郵送する場合、封筒の選び方も重要なポイントです。一般的には、白色の角形2号(A4サイズの書類が折らずに入る大きさ)の封筒を使用します。茶封筒は基本的に社内文書用とされているため、履歴書の送付には適していません。
封筒には「履歴書在中」と赤字で記載し、書類が重要であることを示します。宛先は「〇〇株式会社 人事部 採用担当者様」というように、できるだけ具体的に記載します。また封筒の裏面には差出人の住所、氏名、電話番号を記載することを忘れないようにしましょう。
切手は料金不足にならないよう、書類の重さに応じた適切な金額を貼ります。心配な場合は、郵便局で重さを計ってもらうとよいでしょう。また配達証明や簡易書留などの特殊な郵送方法を利用することで、重要書類が確実に届いたことを確認することもできます。
提出方法別の注意点
履歴書の提出方法には、郵送の他にも持参、メール、ウェブエントリーなどがあります。それぞれの提出方法に応じた注意点があります。
持参する場合は、清潔なクリアファイルや封筒に入れて折り目がつかないように持参します。また受付での対応や担当者との短い会話も第一印象につながるため、身だしなみや言葉遣いにも気を配りましょう。
メールで提出する場合は、PDFなどの一般的なフォーマットで送信し、ファイル名には自分の名前を含めるようにします。例えば「履歴書_山田太郎.pdf」というように、誰の書類か一目で分かるファイル名にすることが大切です。またメールの件名や本文も丁寧に書き、添付ファイルの内容を明記します。
ウェブエントリーの場合は、システムの指示に従って必要事項を入力します。入力内容は一時保存しておき、最終的な送信前に誤りがないか確認することをおすすめします。また送信完了画面や受付完了メールは、応募の証拠として保存しておくとよいでしょう。
採用担当者が求める礼儀とは
履歴書を通じて採用担当者が見ているのは、記載内容だけでなく、応募者の仕事に対する姿勢や基本的なビジネスマナーです。以下のポイントに注意することで、好印象を与えることができます。
まず、提出期限を守ることは最も基本的なマナーです。期限に余裕をもって提出することで、時間管理能力や計画性をアピールすることができます。やむを得ず遅れる場合は、事前に連絡を入れることが大切です。
次に、指定された提出方法や書類のフォーマットを守ることも重要です。例えば、「写真添付」「手書き」などの指定がある場合は、それに従うことが礼儀です。指示に従わない場合、指示を理解する能力や従う姿勢に欠けると判断される可能性があります。
また、履歴書を送付した後のフォローも大切です。1週間程度経っても連絡がない場合は、丁寧に確認の連絡を入れることも一つの方法です。ただし、しつこく連絡することは避け相手の都合を尊重する姿勢を示すことが大切です。
最後に、不採用の場合でも丁寧な対応を心がけましょう。結果に関わらず、選考の機会を提供してくれたことへの感謝の気持ちを示すことで将来的な再応募の可能性を残すことができます。
以上、履歴書における学歴と職歴の順番や記載方法について詳しく解説してきました。履歴書は応募者の第一印象を左右する重要な書類です。この記事で紹介したポイントを押さえて、自分の強みを効果的にアピールする履歴書を作成し採用を勝ち取りましょう。正確で丁寧な履歴書は、応募者の姿勢や仕事に対する真剣さを示す大切なツールです。自信を持って提出できる履歴書を作成することが、就職・転職成功への第一歩となります。



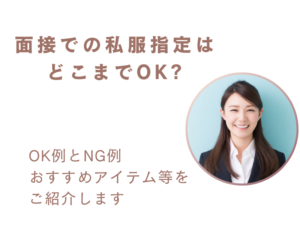
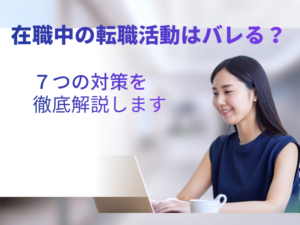
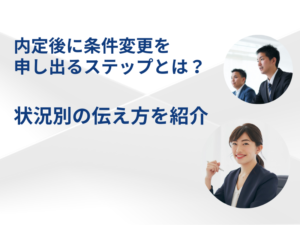

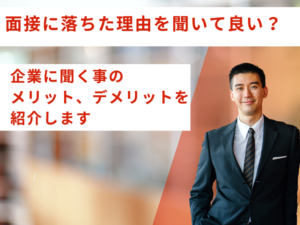

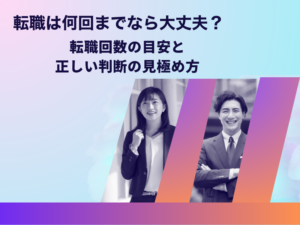
-800-x-600-px-300x225.png)
-Webバナー広告-800-x-600-px-1-300x225.png)

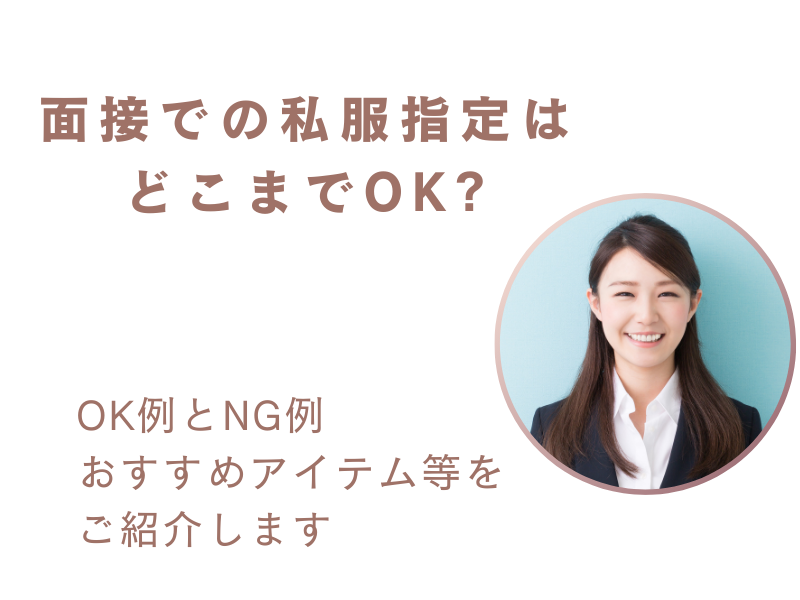
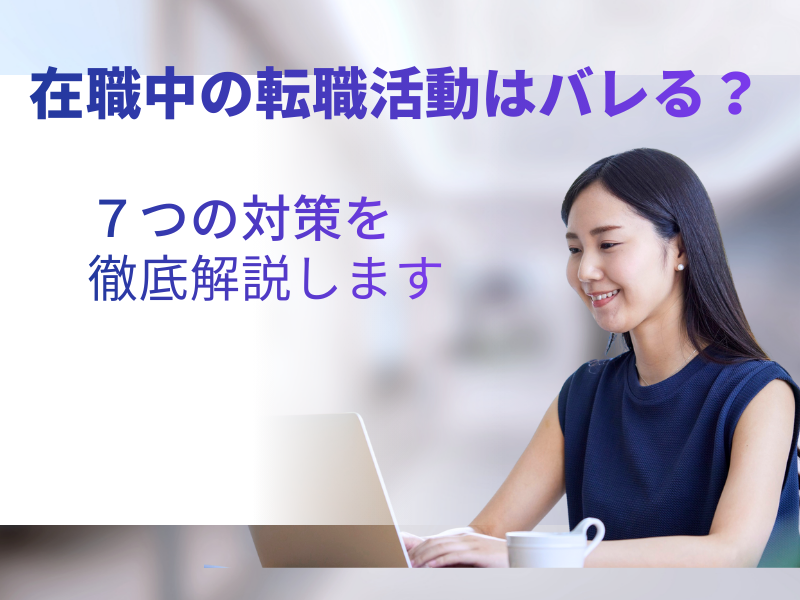
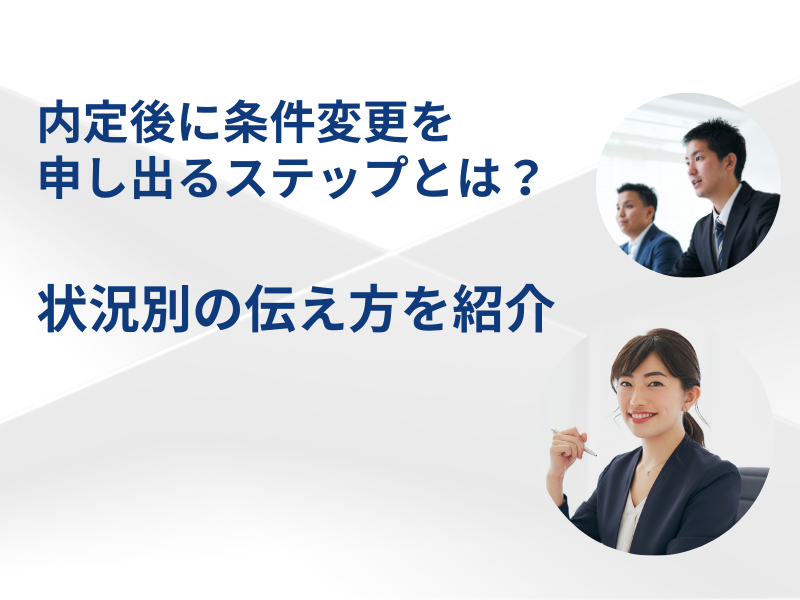

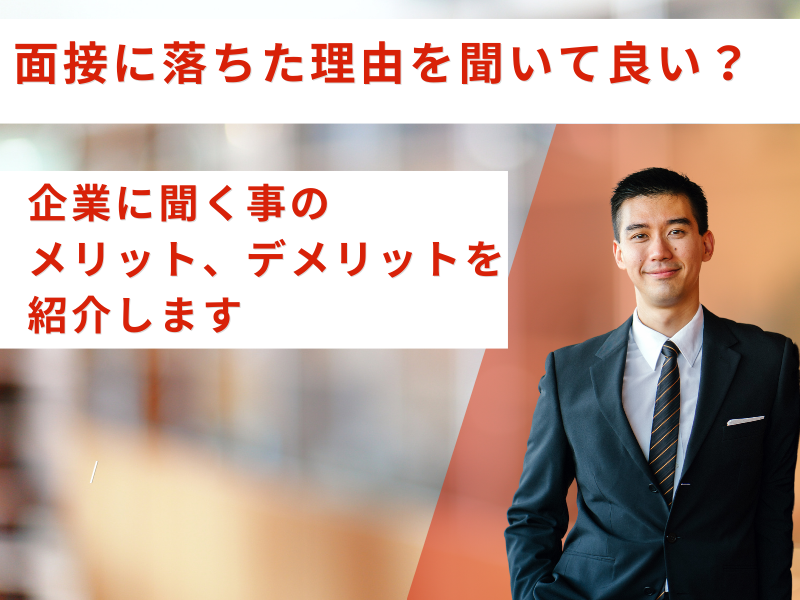

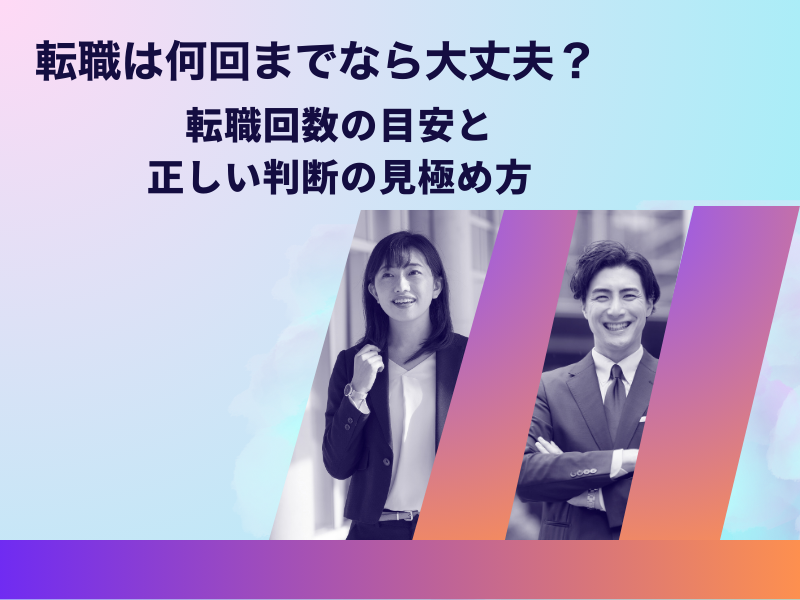
-800-x-600-px.png)
-Webバナー広告-800-x-600-px-1.png)
